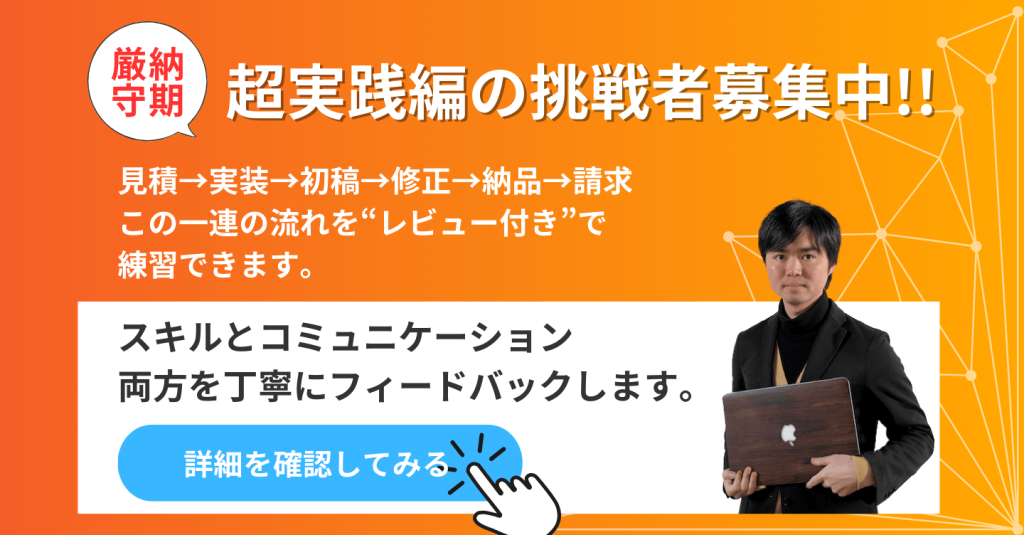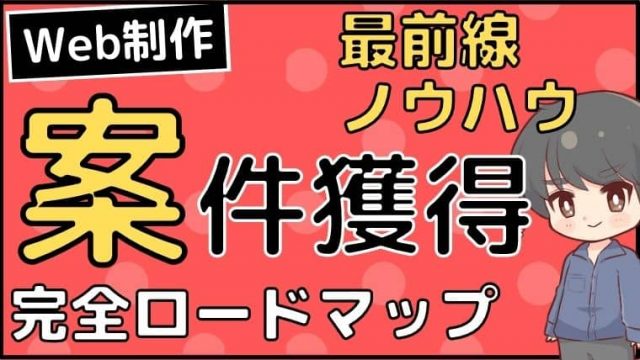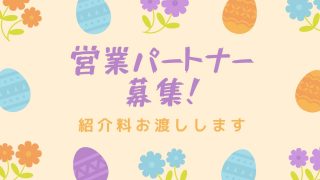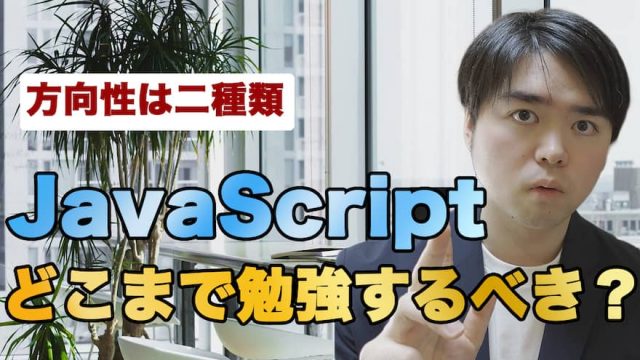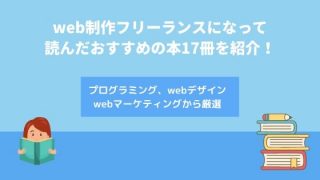こんにちは、現在フリーランスのWeb制作者として6年ほど活動しているしょーごと申します。
まず軽く僕の自己紹介ですが、2018年3月からプログラミング学習を始め、8月よりフリーランスでwebサイトを制作する仕事を行なっており、
現在はHTML、CSS(Sass)、JavaScript、WordPressをメインにお仕事をしています。
これをご覧の方はフリーランスを目指している、または興味がある方が多いかと思います。
私もフリーランスになる前に、いったいどういうところからお仕事をいただくのか全くの謎で、
強いて言えば「クラウドソーシング」をギリ知っていた程度でした。
なので、今回は僕の周りのフリーランスも含めた一般的な事例を紹介するとともに、私自身の事例も紹介して、皆さんの疑問解消の一助になれればと思います。
全部で7つあります。
またそれぞれの手法でメリットデメリットなども同時にお伝えしていきますので、この記事をご覧いただいた後には、
どのように仕事を取っていくのが良いか、具体的イメージができるようになります。
そして最後に「仕事が途絶えないフリーランスの特徴」にも触れていきます。
個人的に、今回の記事は自分で言うのもなんですが、めちゃくちゃ有益情報の集まりだと思うので、
ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いたのは
しょーご(@samurabrass)
このブログ「しょーごログ」の運営者。2018年からエンジニアとしてサイト制作やシステム開発を行いつつ、ブログとYouTubeで情報発信を行っている。駆け出しエンジニアのコーディング課題添削も行う。
\現役エンジニアのレビュー付き/
実践レベルのコーディング課題公開中

- デザインカンプからのコーディングを経験したい
- 現役エンジニアのレビューを受けてみたい
- 即戦力級のポートフォリオを用意したい
2024年にデザインを完全リニューアルしています!
コーディングを学習中の方はぜひご活用ください。
\無料の入門編から本格企業サイトまで/
また、超実践編という鬼のようなコースもあるので、ほぼ実案件と同じ厳しい環境でコミュニケーション面までレビュー受けたい方がいれば、是非。
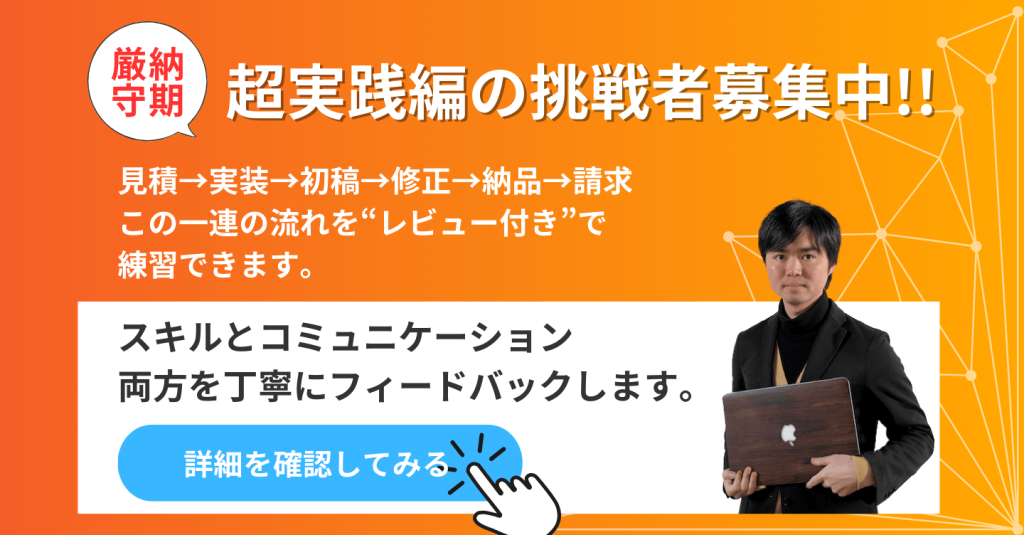
①クラウドソーシング
やはり鉄板というか、多くの人が想像するのがクラウドソーシングかと思います。
最近はクラウドソーシングに対して
- 価格安すぎ
- 地雷クライアントが多い
- 納期が短い
など批判がつきませんが、駆け出しのフリーランスが実務経験を最初に積む段階では非常にいいと感じています。
この辺りに関しては、以前「ほんとは公開したくない、クラウドソーシングで必勝の「ある要素」をお伝えします」という記事で
解説していますので、そちらをご覧いただければと思います。
私の周りのフリーランス歴1年から3年程度のフリーランス仲間を見た感じだと、クラウドソーシングを受注目的で積極的に利用している人はほとんどいないイメージです。
どちらかというと、案件の発注側に回る人はまあまあいるかなという感じですね。
特にデザイン案件などで発注している人が多いです。
私自身の抱える案件のクラウドソーシング率も0-1割程度で、全くない月の方が多いです。
ただ、クラウドソーシングにもおいしい案件がたまにあるんですね。LPコーディング一枚10万円とかですね。
周りのフリーランス含め、基本的にはそういった「おいしい案件」がないか今でも時間があるときには回ったりはしています。
②web制作会社、システム開発会社

web制作フリーランスでもコーディングメインに行なっている人は、ほとんどの人がここを活用しているイメージです。
Web制作会社はWordPressなどでweb制作、システム開発会社はRubyやPHP,Javaなどサーバーサイドも含めて開発しているという文脈でここでは話しています。
制作会社やシステム開発会社が人手の関係で対処できない部分を、私たち外部のフリーランスが制作パートナーになって回してもらうという構造ですね。
制作会社と組むメリット
- 定期的に案件を受注できる
- 制作会社の手法を学べる
大きくこの2つが挙げられると思います。
フリーランスは案件がない=無収入になってしまうので、自分が営業しなくても定期的に案件をいただけるのはありがたいですし、
提携した制作会社が優れたノウハウを持っていれば、そこと仕事をすることでそのノウハウを吸収することも可能です。
ここの変動は結構大きいので、実際に継続して案件をもらえるかはその人の仕事ぶりやその制作会社の繁忙度に左右されたり、
採用している技術もレガシーだったりする可能性もあるので一概には言えませんが、個人的に再現性が高くオススメの方法と言えます。
特にSEO施策などは独学だと限界がありますので、大変勉強になりますね。
内部対策1つとっても、ちゃんとサイトマップに「タイトル」「ディスクリプション」「h1タグ」「対策キーワード」などが記述してあり、「そこまでやるのか」と、駆け出し期は驚きました。
制作会社から受注するデメリット
- 納期が短い場合が多い
- 価格も低い場合が多い
- 基本的に自分の実績にならない
ここも変動が大きいので一概には言えませんが、構造的に外注フリーランスは「下請け」ということになりますから、
ある程度仕方ない部分もあるかなと思います。
特に提携している会社が「二次請け」以下だと、その会社には裁量も予算もないので価格も納期も要件もきつくなる傾向があります。
逆に一次請けの会社と提携できると、ここのデメリットはある程度解消されるのかなと思います。
周りのフリーランス、特にコーダーを見ていると、制作会社をメインにしているフリーランスが結構多いです。
システム開発会社は、JavaScriptフレームワークやGitなど最低限の理解がないと、フロントとして参画するのは難しいので、周りにはそこまでいませんね。
私自身も制作会社数社と提携しており、毎月2,3件程度の制作案件のお話をいただいています。
システム開発会社とはRails案件のフロント担当として一度だけ仕事をしたことがあります。
割合としては案件の4割程度を占めるかなと思います。
Web制作会社営業の最強の教科書を出しました
③フリーランスの知人友人
これは同業のフリーランスからの案件の受注を指しています。
事例としては
- コーディングを外注したいデザイナーやコーダーから受注
- デザインを外注したいデザイナーやコーダーからの受注
が多いのかなと思います。
フリーランスは基本的に一人で作業をするので、案件が集中する人は割とすぐ「キャパシティオーバー」になってしまうんですよね。
私も3月はweb業界自体が繁忙期ということで、案件が死ぬほど来てしまい、全部受けた結果毎日14時間作業する羽目になっています。
そういった人が発注する案件などを受注するということですね。
フリーランスの知人友人から受注するメリット
- 顔なじみの分コミュニケーションコストが低い
初めての人と仕事をすると、結構コミュニケーションの感覚をつかむのに慣れが必要だったりしますが、
フリーランスの知人であれば、相手の人間性などがある程度わかっているし、共有している知識も近いので、案件に関するテキストコミュニケーションもある程度やりやすいです。
フリーランスの知人友人から受注するデメリット
・契約関連をしっかりしていないと問題が起こりやすい
案件が大きい場合は「契約書」のやりとりはしっかりしておいたほうがいいです。
特に「支払い関連」ですね。たまになかなか振り込んでくれないフリーランスもいるようです。
お金が絡むものは大きな問題に発展しやすく、その後の友情に亀裂が入りやすいので、知人友人といえど見積書や請求書といった書類は最低限用いるようにしましょう。
私の「フリーランスの知り合いからの受注」は、最近増えて2割程度です。
④コミュニティからの受注

かなりざっくりしていますが、例えば「カメラ愛好会」に属しているweb制作者が、そのコミュニティでカメラマンのホームページ制作を受注するとか、
地方の商工会に属しているデザイナーが同じ商工会内の経営者から採用パンフレットの作成を依頼される
などですね。
簡単にいうと、「ライバルが誰もいないが需要はある場所で受注する」というのが多いかなと思います。
知り合いにはいませんが、よく「その町にwebデザイナーが一人しかいないから、その町のデザインの仕事が全部その人に行く」とかは
たまに聞きます。
コミュニティからの受注のメリット
- 自分が興味のある分野で制作できる
- コミュニティニッチで仕事が集中する
- 直案件なので、仕事の調整がしやすい
例えば自分がオーケストラに属してるとして、そこの「ホームページを作成する」となると、結構モチベーションは高いと思います。
そもそも自分の好きな分野だし、制作後の運用もおそらく自分でやることになるからです。
また、そのオーケストラ内に自営業者や企業の経営者などがいれば、「うちのも作ってよ」となる可能性は大いになります。
そのコミュニティでweb制作ができるのは、基本的に「あなたしかいない」わけですから、仕事が集中しやすいということになりますよね。
コミュニティからの受注のデメリット
- web制作と相性のいいコミュニティである必要がある
例えば、「web制作者のコミュニティ」とかどうでしょうか。
確かに誰かが「web制作案件」を流してくれるかもしれませんが、周りはみんな同業者。
応募者も大量にいるので、自分が選ばれる確率は少ないです。
逆に「コーダーばかりのコミュニティのデザイナー」や「デザイナーだらけのコミュニティでのコーダー」ならチャンスはおおいにあると思うので、
所属する場所は吟味する必要はあるかなと思います。
私の場合は「地方のコーワキングスペースつながり」で受注したことがあります。
特に地方のコワーキングスペースはスタッフがコミュニティ形成に積極的で「横のつながりが強い」ので、
そこでコミュニティニッチになれれば、仕事を紹介してくれる可能性は高いです。
この辺りは昔記事に書きました。
ちなみに私のコミュニティからの受注の割合としては、1割もないかなと思います。
そこまで多くはないです。
⑤営業パートナー

個人的に今一番力を入れている分野になります。
どういうことかというと、自分にweb制作案件を紹介してくれた人に「利益の一部」を報酬としてお渡しすることで、
営業マンとして動いてもらう方式になります。
ここも詳しくは今後記事にする予定なので、詳しいノウハウは省きますが、営業パートナー募集の記事を以前ブログで書いているので、
きになる方はそちらをご覧いただければと思います。
営業パートナーのメリット
- 直案件なので、中間マージンが取られない
- 納期や期待値調整が非常にやりやすい
- 上流から全て関われる
- パートナーを効率的に稼働させられれば、安定的に受注できる
営業パートナーを活用するメリットはかなり大きいです。
同じ直案件なので、コミュニティでの受注とかぶる部分もありますが、
高単価で無理のない納期で受注できる可能性が高いです。
また、優秀な営業マンと組んだ場合、ここの可能性は無限大で夢があっていいですね。
営業パートナーのデメリット
- 全てまるっと受けるので、デザインやマーケの知見が必要
- 営業パートナーを動かすには工夫が必要
だいたい皆さんTwitterとかブログで募集されたりするんですが、基本的に「報酬を提示」してもなかなかみんなは動いてくれません。
多分友人に直接聞くとわかるんですが、「あれお前そんなこと言ってたっけ?」的な反応をされると思います。
人の情報に対する感度なんて基本はその程度で、ほとんどの人に認知されていないと思います。
また、下請けと違い「売り上げを上げるためのweb周りの総合サポート」的な立ち回りになることが多いです。
ここを楽しめる人は問題ないかと思いますが、会社を実際に訪問したりだとかコンテンツを決めたりデザイン作ったり
導線設計したり、明らかに「コーディング」以外の業務の方が多くなってきますので、人によってはそこがデメリットになるかもしれません。
私はむしろそっちの問題解決の方が本質そうで面白そうなので、今後そちらにシフトしていきます。
私の場合、営業パートナー経由の案件は2割程度です。
個人的にはここを2020年度中に5割以上に増やしたいです。
⑥SNSで受注

最後にSNSで受注です。
主にTwitterやインスタ、Facebook経由ですね。Tinderでマッチングした相手から受注した話もたまに聞きます笑
情報発信をして、何ができるか明確にしていたり人柄が良さげで売れっ子感が出ている人ほど、依頼されやすい気がします。
SNSで受注するメリット
- SNSからなので、相手はこちらのスキル感をある程度は分かっている
- 多くの人に宣伝できる
SNSを利用するメリットは、不特定多数の多くの人に、自分の存在をアピールできることかなと思います。
SNSの活用に関しては、それだけで動画一本になってしまうので避けますが、自分のインプレッション数を上げるためには
いいツールだと思います。
SNSで受注するデメリット
- 自分は相手のことがよくわからない場合が多いので、ヒアリングは綿密にしないとトラブルになりやすい
SNS経由の案件はトラブルも多いです。
特にTwitterだと相手は自分のことを知っているけど、自分は相手のことを知らない場合が多いので、
案件を受ける前に綿密にヒアリングをしてから受注するか判断するべきだと思います。
自分の場合だと昔「中国語でweb制作できる」的なツイートをした時に、「中国人向けのページを作って欲しい」とブログ経由で連絡が来たことがありました。
その時は繁忙期すぎてお断りしてしまったのですが、他にも最近はプログラミングスクールのチューターのお仕事のお声がけをいただく機会が多いのですが、そういったことも日頃のTwitterの投稿あってこそなのかなと思います。
なので、直接SNSで案件が来ることは少なくても、SNSで発信を頑張って信頼値が溜まることで案件が来やすくなる環境を作ることはできるのかなというのが
結論です。
SNS案件の割合としては1割程度ですかね。
⑦フリーランスエージェントを利用した案件獲得

これは既に実務経験がある人向けですが、フリーランスエージェントを使うと、個人では獲得できないような大企業案件を獲得できる可能性があります。
個人的におすすめなエージェント一覧を以下に挙げます。
【第1位】HiPro Tech(公式:https://tech.hipro-job.jp/)
新しめのエージェントながら、フルリモート案件など良質な案件が揃う
【第2位】 レバテックフリーランス(公式:https://freelance.levtech.jp/ )
常駐案件を探すならまずここ!!業界事情にも詳しく、保有している案件の幅も広い。一年以上の実務経験があるならベスト
【第3位】ITプロパートナーズ(公式:https://itpropartners.com/ )
エンド直なので高単価で、週2,3日の案件数はフリーランスエージェントの中でも随一
【第4位】Workship(公式:https://goworkship.com/ )
Web制作系の案件も網羅し、副業参画も可能
【第5位】Midworks(公式:https://mid-works.com/)
他社と比較しても、圧倒的に福利厚生が充実で、リモート案件が充実
例えば「HiPro Tech」はリモート案件が豊富に揃っており、おすすめです。
試しに会員登録して掲載案件を覗いてみると。。。



Web制作スキルで挑戦できる案件が見つけられます。
また、非公開優良案件というのもエージェントは持っているものなので、まずはエージェントに話を聞いてみると、当たりがある可能性が高いです。
まずは「HiPro Tech」以下のエージェントに登録してみてください。
仕事が途切れないフリーランスの特徴
というわけで、以上6つからweb制作フリーランスは仕事を取ってきています。
もう一回まとめると、
①クラウドソーシング
②システム開発会社
③フリーランスの知人友人
④コミュニティからの受注
⑤営業パートナー
⑥SNSで受注
ということですね。
それでは、最後に「仕事が途絶えないフリーランスの特徴」を述べて終わりにしようかと思います。
それは
顧客満足度 – 事前期待値 > 0
これを常に保っているフリーランスになります。
これはぱっと見だと意味がわかりづらいと思うんですが、
つまり「お客さんの想定する120%のクオリティで仕事しろ」ということになります。
それは普段のコミュニケーションもそうだし、納品スピードや納品物のクオリティもそうだし、ささやかな気遣い、人当たりだったり多方面に渡ります。
そういったある種「当たり前のこと」をやっているフリーランスが、継続して発注されるフリーランスだなと、周りを見ていても思います。
これまで述べた6つの案件獲得口いづれも、継続的に仕事がもらえるかはここにかかっているので、この記事を最後にご覧になったあなたにはぜひ、
ここを忘れずに仕事をしてもらい、売れっ子フリーランスになっていただきたいです!
その他案件獲得に役立つ記事一覧
案件獲得の全体ロードマップはこちら
クラウドソーシング・エージェントを全部まとめた記事はこちら
HTML初心者からWordPress実案件レベルまでのコーディング演習課題を「専用ページ」にて公開しています。

- Figma,Photoshopデザインからのコーディング
- サーバーアップロードでサイト公開
- プロによる最大3回の表示確認特典
- レビュー返しは爆速
- 2024年にデザイン刷新!被らないポートフォリオ
「初級編」は初めてデザインからコーディングする方向け
「中級編」はJavaScriptやjQueryの練習
「上級編」はWordPressの実案件を模擬体験できるレベル感にしています。
中級者の方には高難易度課題を詰め合わせた「即戦力セット」も出しています。
全課題で「実務レベルの、プロの厳しいレビュー」を受けられるようにしています。
また、2024年には随時デザインの刷新をしており、完全リニューアル!!
他者と差をつけられるポートフォリオが準備できます!

制作会社も使用する専用レビューツールで分かりやすく添削していきます!
基本的に「まとめて購入」していただくとかなりお得になります↓

コーディングは書籍だけではなかなか実力がつかないので、ぜひ腕試しにご利用ください!!
\課題の購入はこちらから/
また、超実践編という鬼のようなコースもあるので、ほぼ実案件と同じ厳しい環境でコミュニケーション面までレビュー受けたい方がいれば、是非。